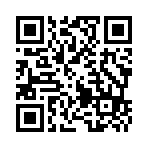スポンサーリンク
ゲッベルスと私 11月30日の座談会
2018年12月02日
前後しますが、11月30日の座談会でのお話を箇条書きにしたものです。
みなさま、それぞれに仕事や用事などでお疲れの夜から、さらに2時間近くも映画をご覧いただき、本当にありがとうございました。
うまくまとめられず、言葉不足だったり、違う解釈をしていることもあるかと思いますが、伺った内容をまとめさせていただきました。
( )内は、補足説明です。
・(ポムゼルさんが)自分の生涯を語ってくれたのが、私たちにとっては有り難いこと。原爆が落とされた広島の人たちは、話すことも恐怖だと言っていた。話すことの大切さを感じた。
・感情的に揺さぶられる映画。(映画中でポムゼルさんの独白の間に挟まれる)アーカイブが興味深かった。独白の中で、ショル兄弟がギロチンにかけられた話がでてきたが、そういえば、白バラ運動の本を買って積ん読になっていたので、かえったら読もうと思う。(白バラ運動とは、第二次世界大戦中のドイツにおいて行われた非暴力主義の反ナチ運動)
・記録映画として貴重。知らないことは怖い。
・淡々とした映画のつくりが、かえって怖い。民衆をスポーツなどに熱狂させていくが、冷静になるのが必要だと思った。
・知らなかった、という言葉が印象的。でも知らないでは済まされない。
・淡々と話されていたので、残ったものが…? 自分もあの状況におかれたら、あのようになるよな~。身近なところで戦争は反対といえる状況をつくっていくことが大切。
・貴重な話。考えることができた。話してくれなかったらと思うと、経験者の話を残していくのは大切。忘れないよう、考えて続けて。
これは毎回同じなのですが、見終わって、すぐ「感想を」と言われても、なかなか言葉にできないところをお聞かせいただき、ありがとうございました。
みなさま、それぞれに仕事や用事などでお疲れの夜から、さらに2時間近くも映画をご覧いただき、本当にありがとうございました。
うまくまとめられず、言葉不足だったり、違う解釈をしていることもあるかと思いますが、伺った内容をまとめさせていただきました。
( )内は、補足説明です。
・(ポムゼルさんが)自分の生涯を語ってくれたのが、私たちにとっては有り難いこと。原爆が落とされた広島の人たちは、話すことも恐怖だと言っていた。話すことの大切さを感じた。
・感情的に揺さぶられる映画。(映画中でポムゼルさんの独白の間に挟まれる)アーカイブが興味深かった。独白の中で、ショル兄弟がギロチンにかけられた話がでてきたが、そういえば、白バラ運動の本を買って積ん読になっていたので、かえったら読もうと思う。(白バラ運動とは、第二次世界大戦中のドイツにおいて行われた非暴力主義の反ナチ運動)
・記録映画として貴重。知らないことは怖い。
・淡々とした映画のつくりが、かえって怖い。民衆をスポーツなどに熱狂させていくが、冷静になるのが必要だと思った。
・知らなかった、という言葉が印象的。でも知らないでは済まされない。
・淡々と話されていたので、残ったものが…? 自分もあの状況におかれたら、あのようになるよな~。身近なところで戦争は反対といえる状況をつくっていくことが大切。
・貴重な話。考えることができた。話してくれなかったらと思うと、経験者の話を残していくのは大切。忘れないよう、考えて続けて。
これは毎回同じなのですが、見終わって、すぐ「感想を」と言われても、なかなか言葉にできないところをお聞かせいただき、ありがとうございました。
ゲッベルスと私、12月1日の座談会
2018年12月02日
「ゲッベルスと私」、たくさんの方にご来場いただきまして、ありがとうございました。
スタッフの晶子さんがまとめてくれた、きのう12月1日の座談会のようすです。

おかげさまで、つきいちシネマ二周年特別企画『ゲッベルスと私』の上映が終了しました!
今回もたくさんの方にご協力いただき、心から感謝します✨
今日の座談会のようすをまとめました。
長いですが、参加できなかった方も含めぜひご覧ください♪
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
一言一言、お気持ちに合う言葉を一生懸命探しておられた参加者のみなさん。
みなさんのお氣持ちをうまくお伝えできるかわかりませんが、どうぞご覧ください。
残念ながら参加できなかった方も、思うところあればぜひコメントでご参加ください。
まずは、この映画の上映をすすめ、配給元との交渉にあたったスタッフから。
・この映画は試写も含めて4回観たが、正直なところ本当はわかっていないところも多いと思う。
ファシズムという転がりだした車は、走りはじめたらもう止められない。ではどうしたらいいのか、ずっと考えてきた。そうなる前に「やだな」「おかしいな」という気持ちを周りの人と話し、連帯して、なんとしてでも食い止めたい。
・難しい映画で、1回ではわからないかもしれないが、中高生などに観てもらいたい。
世の中のおかしい流れ、食い止めるにはどんどん声を上げていくことかと。
・難しいテーマ。人の心・理性というものが麻痺してしまうものなんだな。
歴史・事実を忘れないこと。そういうことがあったと知り、受けとめることからだと思う。
・(ポムゼルさんは自覚なく戦争に巻き込まれていったが)自分も同じ立場になった時にそういうことがあるかも、と思った。
最近、集団で弁護士を罷免する訴えをした事件があったが、ほとんどの人たちは「自分が正義をするつもりでやった」と言っていた。「正義のつもり」でいろんなことが行われる。
自分が「いつか死ぬ」と思うようになった。名誉などではなく、「自分はどう生きたか」で自分の行動をおこしたい。
ポムゼルさんが生きてくれて、話してくれて、感謝したい。
・『ゲッベルスと私』の「私」を自分に置き換えて…。
虐殺や戦争は、自分には遠い話だと感じるが、今自分をとりまく世の中全体の流れが「おかしくないか?」と日々感じている。こういう話は、身近な人とは話せるが、町内会とか少し公の場所ではなかなか言う場面がない。
子育てしながらも、年々厳しくなっていると感じることもある。なかなかいろんな人と話せることがない。
「これからも一緒に考えてください」
・「わたしは何も知らなかった」というポムゼルさんの言葉。
日本の戦争もそうだった。
兄弟6人のうち、上3人は戦争で亡くしている。そんな中親の気持ちを感じながら育って来た。
今、自分の孫たちの将来が安心できるとは思えない。身近な人2〜3人でも「変だよね」と言い合う機会を増やしたい。
・ピーター・ドラッガー(「マネジメント」の著者、ユダヤ系オーストリア人)の勉強会に行ったばかりで、重なるものがああった。資本主義・社会主義があやふやな時代、全体主義が勢いをつけていった。
日本のインパール侵攻の時も、同じような「思考停止」という心理状態だったと聞いた。
重たい映画だったが、勉強になった。
・関西での大学時代に、平和学習と環境問題にどっぷり浸かっていたが、久しぶりに勉強しにきた。日本は原爆ドームが存在するので、勉強しやすい環境だと思う。
「わたしは何も知らなかった」とあるが、ポムゼルさんが観光であれなんであれ、1日でもドイツ国外に出ていたら違っていたかなと思った。
・「わたしは何も知らなかった」なんてありえないでしょう…映画を観る前は思っていたが、もしかしたらそうだったのかもと思った。
今でも、新聞の見出しになっているようなことでも関心がなければ「なんのこと?」となるし、「これがどこへつながっているか」想像力がなければそうなるかも。
海外の人の方が、日本が変わってきているのを感じている。
もう1回観たい。
・頭が漠然としていてパンク寸前。
ナチスドイツは無農薬の野菜を推奨していたりという話を聞いた。いいこともしている。
だけど今は消化しきれない。ゆっくりと消化する。
★ここで、ナチスドイツの「無農薬」や「社会福祉」政策や「労働政策」も長けていたという話に。
しかし、常に生け贄を作っていたのではないか、「国民」にとってはいいのかも、江戸時代の政策に似ているのか?ポルポト派も排除と選別の政策だったなど、みなさんの知識からイロイロ教えていただきました!
・戦時中というのは、わたしたちの今の日常とは全く切り離された別のものだと思っていたが、同じような普通の生活の中に戦争があった・戦争と日常は平行して存在していたとわかった。
無農薬の話があったが、農薬ははじめ「化学兵器」から派生したものだったし、今のタリバンも市民を掌握するためにいろんな「いいこと」をしていたと聞いた。
本を読んでから映画を観た。「知らなかった」とポムゼルさんは言うが、「知りたくなかった」のか「知ろうとしなかった」のか結局わからなかった。自分でもそう思うことがたくさんあり、近い存在に思えた。
(ポムゼルさんは)秘書として仕事にプライドを持っていたというが、「いい仕事」はどこにつながっているのか、もう一度立ち止まって考えたい。
・先日勉強会で「アイヒマン」についてとりあげたところだった。どちらにも言えるのは「自分には関係ない」という言葉と「無感情」。
神聖ローマ帝国でやっていた「無表情育児」をヒトラーもやろうとした。その子どもたちは早くに亡くなったという(★ルーマニアのチャウシェスク政権でも「無表情育児」を推進したとのこと。こちらも子どもは長く生きられなかったそう)
「他人事の感情」自分が世界につながっているという自覚がない。それを言えば、現在の方がもっと無関係・無表情の世の中のような氣がする。
・もっといいお給料を求めて「ナチ党」に入り秘書の仕事をした話を聞いて、「ポイントたくさんもらえるからあの店で買い物しよう」というわたしの日常とあまり変わらないような氣がした。
「どこへつながっているか」の想像力が大事という意見に共感。
・重い映画だった。
感じるのは「想像する」ことがかけていること。
防災に関しても、都合の悪いこと、思い出したくないことを忘れてしまう。こういう映画を観ることで思い出せる。
日常の生活の中で、テレビでもネットでも、情報がありすぎて皆が判断しかねている。心の目で見て聞いてほしいとあらためて感じる。
その後も、スタッフにより補足情報。
・映画では103才だったポムゼルさんがこの映画に満足していたようすだった。(映画の完成を待ったかのように106才でお亡くなりになった)
・先日のアーサー・ビナードさんの講演会でも話が出たが、ヒトラーが作った「バイエル」という会社は、現在「モンサント」という大手の会社を買収して種や農薬の世界的企業のトップに立ったとのこと。
映画の中の時代、民主主義は手続きがめんどくさく幻滅している人が多かったことから、カリスマ的で独裁的な指導者がもてはやされたが、議論を惜しまずにいろんな話し合いをできる機会にしたいとの言葉で締めくくられました。
みなさんの言葉から、どんどん思い出されて意見が飛び出しました。スタッフ一同、みなさんのご参加に心から感謝しています!ありがとうございました!
スタッフの晶子さんがまとめてくれた、きのう12月1日の座談会のようすです。

おかげさまで、つきいちシネマ二周年特別企画『ゲッベルスと私』の上映が終了しました!
今回もたくさんの方にご協力いただき、心から感謝します✨
今日の座談会のようすをまとめました。
長いですが、参加できなかった方も含めぜひご覧ください♪
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
一言一言、お気持ちに合う言葉を一生懸命探しておられた参加者のみなさん。
みなさんのお氣持ちをうまくお伝えできるかわかりませんが、どうぞご覧ください。
残念ながら参加できなかった方も、思うところあればぜひコメントでご参加ください。
まずは、この映画の上映をすすめ、配給元との交渉にあたったスタッフから。
・この映画は試写も含めて4回観たが、正直なところ本当はわかっていないところも多いと思う。
ファシズムという転がりだした車は、走りはじめたらもう止められない。ではどうしたらいいのか、ずっと考えてきた。そうなる前に「やだな」「おかしいな」という気持ちを周りの人と話し、連帯して、なんとしてでも食い止めたい。
・難しい映画で、1回ではわからないかもしれないが、中高生などに観てもらいたい。
世の中のおかしい流れ、食い止めるにはどんどん声を上げていくことかと。
・難しいテーマ。人の心・理性というものが麻痺してしまうものなんだな。
歴史・事実を忘れないこと。そういうことがあったと知り、受けとめることからだと思う。
・(ポムゼルさんは自覚なく戦争に巻き込まれていったが)自分も同じ立場になった時にそういうことがあるかも、と思った。
最近、集団で弁護士を罷免する訴えをした事件があったが、ほとんどの人たちは「自分が正義をするつもりでやった」と言っていた。「正義のつもり」でいろんなことが行われる。
自分が「いつか死ぬ」と思うようになった。名誉などではなく、「自分はどう生きたか」で自分の行動をおこしたい。
ポムゼルさんが生きてくれて、話してくれて、感謝したい。
・『ゲッベルスと私』の「私」を自分に置き換えて…。
虐殺や戦争は、自分には遠い話だと感じるが、今自分をとりまく世の中全体の流れが「おかしくないか?」と日々感じている。こういう話は、身近な人とは話せるが、町内会とか少し公の場所ではなかなか言う場面がない。
子育てしながらも、年々厳しくなっていると感じることもある。なかなかいろんな人と話せることがない。
「これからも一緒に考えてください」
・「わたしは何も知らなかった」というポムゼルさんの言葉。
日本の戦争もそうだった。
兄弟6人のうち、上3人は戦争で亡くしている。そんな中親の気持ちを感じながら育って来た。
今、自分の孫たちの将来が安心できるとは思えない。身近な人2〜3人でも「変だよね」と言い合う機会を増やしたい。
・ピーター・ドラッガー(「マネジメント」の著者、ユダヤ系オーストリア人)の勉強会に行ったばかりで、重なるものがああった。資本主義・社会主義があやふやな時代、全体主義が勢いをつけていった。
日本のインパール侵攻の時も、同じような「思考停止」という心理状態だったと聞いた。
重たい映画だったが、勉強になった。
・関西での大学時代に、平和学習と環境問題にどっぷり浸かっていたが、久しぶりに勉強しにきた。日本は原爆ドームが存在するので、勉強しやすい環境だと思う。
「わたしは何も知らなかった」とあるが、ポムゼルさんが観光であれなんであれ、1日でもドイツ国外に出ていたら違っていたかなと思った。
・「わたしは何も知らなかった」なんてありえないでしょう…映画を観る前は思っていたが、もしかしたらそうだったのかもと思った。
今でも、新聞の見出しになっているようなことでも関心がなければ「なんのこと?」となるし、「これがどこへつながっているか」想像力がなければそうなるかも。
海外の人の方が、日本が変わってきているのを感じている。
もう1回観たい。
・頭が漠然としていてパンク寸前。
ナチスドイツは無農薬の野菜を推奨していたりという話を聞いた。いいこともしている。
だけど今は消化しきれない。ゆっくりと消化する。
★ここで、ナチスドイツの「無農薬」や「社会福祉」政策や「労働政策」も長けていたという話に。
しかし、常に生け贄を作っていたのではないか、「国民」にとってはいいのかも、江戸時代の政策に似ているのか?ポルポト派も排除と選別の政策だったなど、みなさんの知識からイロイロ教えていただきました!
・戦時中というのは、わたしたちの今の日常とは全く切り離された別のものだと思っていたが、同じような普通の生活の中に戦争があった・戦争と日常は平行して存在していたとわかった。
無農薬の話があったが、農薬ははじめ「化学兵器」から派生したものだったし、今のタリバンも市民を掌握するためにいろんな「いいこと」をしていたと聞いた。
本を読んでから映画を観た。「知らなかった」とポムゼルさんは言うが、「知りたくなかった」のか「知ろうとしなかった」のか結局わからなかった。自分でもそう思うことがたくさんあり、近い存在に思えた。
(ポムゼルさんは)秘書として仕事にプライドを持っていたというが、「いい仕事」はどこにつながっているのか、もう一度立ち止まって考えたい。
・先日勉強会で「アイヒマン」についてとりあげたところだった。どちらにも言えるのは「自分には関係ない」という言葉と「無感情」。
神聖ローマ帝国でやっていた「無表情育児」をヒトラーもやろうとした。その子どもたちは早くに亡くなったという(★ルーマニアのチャウシェスク政権でも「無表情育児」を推進したとのこと。こちらも子どもは長く生きられなかったそう)
「他人事の感情」自分が世界につながっているという自覚がない。それを言えば、現在の方がもっと無関係・無表情の世の中のような氣がする。
・もっといいお給料を求めて「ナチ党」に入り秘書の仕事をした話を聞いて、「ポイントたくさんもらえるからあの店で買い物しよう」というわたしの日常とあまり変わらないような氣がした。
「どこへつながっているか」の想像力が大事という意見に共感。
・重い映画だった。
感じるのは「想像する」ことがかけていること。
防災に関しても、都合の悪いこと、思い出したくないことを忘れてしまう。こういう映画を観ることで思い出せる。
日常の生活の中で、テレビでもネットでも、情報がありすぎて皆が判断しかねている。心の目で見て聞いてほしいとあらためて感じる。
その後も、スタッフにより補足情報。
・映画では103才だったポムゼルさんがこの映画に満足していたようすだった。(映画の完成を待ったかのように106才でお亡くなりになった)
・先日のアーサー・ビナードさんの講演会でも話が出たが、ヒトラーが作った「バイエル」という会社は、現在「モンサント」という大手の会社を買収して種や農薬の世界的企業のトップに立ったとのこと。
映画の中の時代、民主主義は手続きがめんどくさく幻滅している人が多かったことから、カリスマ的で独裁的な指導者がもてはやされたが、議論を惜しまずにいろんな話し合いをできる機会にしたいとの言葉で締めくくられました。
みなさんの言葉から、どんどん思い出されて意見が飛び出しました。スタッフ一同、みなさんのご参加に心から感謝しています!ありがとうございました!